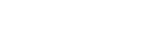新着情報
 Information
Information
海外医療制度勉強会 9期を開催します
海外医療制度勉強会 第9期(2025年10月~2026年3月)
📅 毎月第3木曜の夜に開催!
世界を旅する6か月 ~ニュージーランドからカンボジアまで~
欧州にとどまらず、アジア・オセアニア・中南米・途上国を横断!
今回はまさに「地球規模の医療制度ツアー」です。
申込:https://mizohiro-9round.peatix.com/
割引コード:mizohiro1018
数に制限がありますが、割引コードもご用意しました。
ご興味頂けましたら、是非ご参加ください。
第9期概要
ニュージーランドの地域包括ケア型、アイスランドの小国集中モデル、香港の二層構造、コスタリカの皆保険成功例、コロンビアの混合制度、そしてカンボジアの途上国型——。
制度はまったく異なりますが、どの国も「持続可能な医療」をめぐる同じ問いに挑んでいます。
医療制度は各国の歴史や価値観にも大きく影響をしています。
第9期は、制度の違いを知るだけではなく、各国の歴史・文化・価値観までも映し出す知的な旅。
世界の『医療制度の物語』を一緒に体験しませんか?
🌟 この勉強会で得られること🌟
1)豊富な解説事例のPDF資料が毎回ついてくる! スライド枚数は毎回100枚超!
2)毎回、アーカイブ配信があるよ! 何回でも見直しができちゃうから、欠席回も安心!
3)海外の医療制度を勉強すると、日本の制度についての解像度が爆上がり! 仕事にも役に立つよ!
4)質疑応答も盛り上がるよ! セミナー終了後、質疑応答は質問尽きるまで延々に続くよ!
5)自分で調べるより、早くて簡単! 参加費は「時間を買った」と考えよう!
★第9期のラインナップ★
10月 ニュージーランドの医療制度『GPが国を動かす!』
ニュージーランドは英国型のGP制度をベースにしつつ、より強く「国全体での地域包括ケア」へと舵を切った点が特徴です。
GPは単なるゲートキーパーにとどまらず、地域保健看護師やMāoriヘルスプロバイダーと連携し、生活習慣病予防から慢性疾患管理までを包括的に担います。
また、医療提供体制の再編により、全国をカバーするPrimary Health Organisation (PHO)が構築され、資金配分もここを通じて行われています。
英国や豪州に比べて、制度として「地域包括ケア」を徹底的に仕組み化した点こそがニュージーランドモデルのユニークさです。
小国だからこそ可能となった、精緻に制度化された「GP+地域連携」の姿を深掘りします。
今回のアンケート第2位の国です。
11月 アイスランドの医療制度『人口37万人、国全体が一つの病院!』
アイスランドは北欧諸国の中で最小の人口規模を持ち、全国民が37万人という「実験場」のような国です。
制度の基盤は公的財源による一元管理で、首都レイキャビクの大学病院がほぼ国立中枢病院として機能し、専門医療を一手に担っています。
小国ゆえに全分野の専門医を国内で揃えることは不可能であり、心臓外科や小児がん治療などは今もデンマークなど周辺国に委託する体制です。
一方で、国民の健康指標は世界最高水準を誇り、「国内集中+国外依存」のバランスが極めてうまく機能しているのが特徴。
北欧諸国の最後のピースとして、スウェーデンやデンマークの「分権型」と比較することで、そのユニークさが浮かび上がります。
今回のアンケート第3位の国です。
12月 香港の医療制度『住民の9割が公立病院に並ぶ都市』
香港の医療は、HA(Hospital Authority:病院管理局)によって統括される公立病院群と、自由市場に任せられた民間医療という、はっきり二分された構造を持ちます。
人口の9割以上がまず公立病院を利用し、外来診察料は数十香港ドル(数百円)と極めて低廉。
一方で待機時間は長く、救急から入院、がん治療に至るまで「公共インフラ」として機能します。
対照的に、富裕層や外国人駐在員は、国際水準のホテル並みサービスを備えた民間病院を利用。
支払いは自己負担か民間保険で、価格は欧米並みに高額です。
シンガポールのように国民全体が階層的に民間利用へ誘導されるのではなく、香港は「大多数=公立、少数=民間」という極端な分化を前提に制度が組み立てられている点が特徴です。
その結果、医療提供の公平性は確保されつつも、財政負担・人材流出・待機時間の長期化といった構造的課題を常に抱えています。
今回のアンケート第1位の国です。
1月 コスタリカの医療制度『軍を捨て、皆保険に賭けた国』
コスタリカは1949年に常備軍を廃止し、その財源を教育と医療へ集中投資してきました。
その結果、GDP規模は中米で中堅にすぎないにもかかわらず、平均寿命はアメリカを上回り、国民の健康指標は世界でも高水準を誇ります。
制度の中核を担うのは コスタリカ社会保険基金(CCSS)。
ここが保険料の徴収から病院運営までを一元的に管理し、公立病院・診療所ネットワークを通じて国民全員にサービスを提供しています。
財源は賃金に対する保険料と国庫負担で賄われ、医療・年金・福祉を包括的にカバーする“ワンストップ社会保障”が最大の特徴です。
さらにコスタリカは早くから プライマリケア重視 を徹底。
1990年代に「基礎医療チーム(EBAIS)」を全国に配置し、医師・看護師・地域保健員がチームで住民を継続管理する仕組みを整えました。
これにより僻地の住民も漏れなく医療サービスにつながり、感染症対策や慢性疾患管理で大きな成果をあげています。
「軍を捨てて社会保障を取る」という国家的選択。
それが可能にした“中米の奇跡”こそ、コスタリカの医療制度の本質です。
今回のアンケート第5位の国です。
2月 コロンビアの医療制度『競争で皆保険を実現した実験場』
1990年代初頭、医療アクセスが限られ、国民の多くが無保険状態にあったコロンビア。
そこで1993年に大改革が行われ、全国民に保険加入を義務づける制度が導入されました。
制度の仕組みはユニークで、拠出制(給与から保険料を払う層)と、国の補助で加入する補助制(低所得層)の二本立て。
それを運営するのは「EPS」と呼ばれる民間保険者で、国民は自分が加入するEPSを選び、EPSが契約した病院(IPS)で診療を受ける仕組みになっています。
この制度によって、加入率はほぼ100%に到達し、医療アクセスは大きく改善しました。
一方で、EPSの経営破綻や財源不足、都市部と農村部の格差など、課題も山積。
「競争を導入して皆保険を実現した実験国家」として、成功と混乱が同居するのがコロンビアの特徴です。
今回のアンケート第4位の国です。
3月 カンボジアの医療制度『制度なき医療が問いかける医療の原点』
カンボジアは1970年代のポル・ポト政権下で、医師や医療人材の多くを失うという未曾有の断絶を経験しました。
その後の再建は、国際援助とNGO活動に大きく依存しており、いまなお医療現場の基盤の多くが海外からの支援で成り立っています。
都市部のプノンペンでは私立病院や国際クリニックが急速に発展し、富裕層や外国人向けの高額医療が提供される一方、農村部では保健センターの設備不足や人材不足が深刻で、ワクチン接種や母子保健といった基礎的なサービスすら、国際機関の支援なしには持続が難しい状況です。
保険制度はまだ発展途上で、公的な「国民健康保険」のような枠組みは未整備。
一部で地域保健基金やマイクロ保険の試みがありますが、カバー率は低く、現金払い(アウト・オブ・ポケット)が一般的です。
こうした現状は、他のASEAN諸国が「国民皆保険」や「積立方式」に移行している流れと対照的。
制度が整っていないからこそ、「医療とは何か」「誰が支えるのか」という原点を考えさせられる国でもあります。
今回のアンケート第6位の国です。
第9期は「多様な制度を巡る知的な旅」がテーマです。
小国の集中モデルから途上国の再生、自由市場と公立のせめぎ合いまで、驚きと学びが詰まった6か月です。
参加者 三大特典!
1) スライド資料(PDF) 毎回150枚以上、 大ボリューム
2) アーカイブ配信(参加見逃しでも大丈夫!)
3) 毎年恒例 日本の医療制度の優待参加!