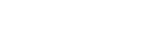新着情報
 Information
Information
弊社代表の溝口博重が、いい病院の研究会で「高額療養費制度の上限引き上げ」に関する講演を実施しました
【講演開催報告】
「高額療養費制度の上限引き上げ問題を読み解く ~制度創設の経緯と、改革なき負担増の本質~」
2025年3月18日、「いい病院の研究会」(主催:一般社団法人あいつなぐ)にて、「高額療養費の上限引き上げ問題」をテーマとした講演を行いました。
今回の講演では、日本の医療制度における「高額療養費制度」がどのように誕生・発展してきたのか、その制度的な意義を振り返るとともに、昨今進められている上限額引き上げの背景とその本質について多角的に検討しました。
講演の内容
Ⅰ.高額療養費制度の成り立ちと意義
① 国民皆保険制度と「最後の安全網」
1961年に実現した国民皆保険制度の下で、医療費の急増により生活困難に陥る世帯を救済するため、1973年に高額療養費制度の前身となる「高額療養費に対する給付制度」が創設されました。
その後も段階的に改正が加えられ、現代の高額療養費制度が整備されました。
② 制度の目的と公平性の仕組み
この制度は、所得に応じた自己負担限度額を設けることで、医療アクセスの公平性と家計の保護を両立するものとして長年機能してきました。
高齢者・低所得者・現役世代といった層ごとのバランスにも配慮された制度設計となっています。
Ⅱ.近年の「上限額引き上げ」の背景と課題
① 少子化対策と財源確保の現実
今回の上限額引き上げは、一見すると制度改革の一環に見えますが、実際には少子化対策の財源捻出を目的とした「財政調整的措置」であり、本来の医療制度改革とは異なる軸で進められています。
② リスク分担の原則からの逸脱
講演では、社会保険制度が本来持つ「加入者間のリスクシェア(共助)」という原則から外れ、少子化対策のように世代間で利益を享受しない支出*保険料を充てる点についても批判的に解説。
保険制度の信頼性や透明性が損なわれる懸念を指摘しました。
Ⅲ.制度の持続可能性と国民の納得感
① 負担増だけの改革は「改革」と呼べるか
単なる負担増では、制度への納得感や信頼を得ることは困難です。制度の持続性を名目に進められる措置であっても、改革なき負担増は将来的に制度そのものの崩壊を招く可能性があると警鐘を鳴らしました。
② 改革には制度全体の再設計が不可欠
今回の上限額引き上げは、制度設計の目的や理念との整合性を欠いた“場当たり的な施策”とも言えます。
講演では、将来世代に制度を引き継ぐためには、構造的な見直しや合意形成のプロセスが不可欠であることを訴えました。
ご参加いただいた皆さま、ありがとうございました。
今後も、社会保障制度の本質を見つめ直し、制度の持続可能性と公平性を両立するための学びの場を提供してまいります。