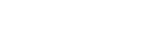新着情報
 Information
Information
【海外医療制度勉強会】「ニュージーランドの医療制度2025」
【実施報告書】海外医療制度勉強会(ニュージーランド編)
2025年10月16日、海外医療制度に関する勉強会を実施し、今回は「ニュージーランド(New Zealand)」の医療制度をテーマに取り上げました。
講師は弊社代表の溝口博重が務めました。
参加者は医療従事者、行政関係者、学生、医療関連ビジネスに関心を持つ方々など計48名でした。
第1章:国家構造と制度文化の背景
ニュージーランドは議会制民主主義・コモンロー(英米法系)を基盤としつつ、特徴的なのは「国家とコミュニティの共同統治」という制度文化です。
特に先住民族マオリをはじめとする多文化社会の中で、「公平性(Equity)」よりも「実質的格差是正(Equity in Outcomes)」を重視する姿勢が見られます。
医療制度の根底には以下の価値観が根付いています。
ユニバーサルヘルスは“権利”であり、個々人の経済力に左右されるべきではない
国家の役割は「直接給付」ではなく「地域・医療機関への委託と補助」
マオリ・太平洋系など民族グループへの“ターゲティング政策”が前提
第2章:制度変遷と構造転換
ニュージーランド医療制度の変遷は以下の3フェーズに整理できます。
1)1938年「Social Security Act」~ 世界初のユニバーサルヘルス制度を法制化
2)1990年代~ 民営化改革により市場競争導入(PHO構想の前身)
3)2001年以降~ **PHO(Primary Health Organisation)**を軸とした地域包括ケア型システムに転換
現在は「全国一本化された公的医療制度+民族別のターゲティング支援」へ再統合が進んでおり、2022年にはDHB(地方保健局)を廃止して国立機構『Te Whatu Ora』に一本化しています。
第3章:国民皆保険とリスク共有の仕組み
日本のように「保険料を徴収して加入する」という形式的な皆保険制度は存在しません。
医療費の大半は『税方式(General Taxation)』で賄われる
国民は保険証を持たず、住民であれば自動的に公的医療の対象
一方で、民間保険加入率は約33%と高く、主に「待ち時間短縮・個室確保」目的で利用されます
また、薬剤費は「$5薬制度」と呼ばれ、対象薬は1処方あたり5ドル(約450円)で上限負担が設定されています。
第4章:医療提供体制と地域ケア
α:プライマリ・ケア(GP登録制)
GP(General Practitioner)が必須登録制となっており、かかりつけ医がゲートキーパーとして機能します。
診療所は民間開業形態が中心ですが、PHOと契約して公費診療を提供します。
β:病院・二次医療
急性期病院の大半は公立(Te Whatu Ora傘下)ですが、公私混合病床構造となっています。
専門医紹介には数週間〜数ヶ月かかることもあり、民間保険が『待機時間回避ツール』として機能。
γ:薬局制度
薬局は完全民営ですが、薬価上限制度(Pharmac)が国家的に統制。
薬剤採用は極めて厳しく、「費用対効果ベースの国民的議論」が行われます。
δ:在宅・長期ケア
Home Support Servicesにより、一定時間までの在宅介護を無料または低額提供。
施設介護は民営中心+公費補助(Residential Care Subsidy)。
第5章:医師教育・診療報酬・長期ケア制度
医師教育:PGY1/PGY2制度は日本の初期研修に類似。欧州・豪州へも国際移動が容易。
診療報酬:GPはCapitation(人口当たり定額)+FFS(出来高)のハイブリッド。
病院はグローバルバジェット型(包括予算)。
長期ケアは介護保険制度なし。医療・福祉・公的補助が混在した柔軟運用。
第6章:質疑応答・参加者の声
「国籍・所得に関係なく『住民』なら医療を受けられる制度設計は、日本の議論と根本的に違う」
「待機時間の長さが課題とされる一方、『命に関わるものは即時対応』という線引きが明確で安心感がある」
「マオリなど少数民族向けに“別枠予算”があるのは、単なる平等ではなく『結果の公平』を目指す姿勢だと感じた」
次回予告
来月は「北欧アイスランド」の医療制度を取り上げます。
国民負担率世界トップレベルの福祉国家が、なぜ高い満足度を維持できるのか。財源構造と国民意識を深掘りします。