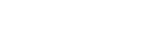新着情報
 Information
Information
【海外医療制度勉強会】「オランダの医療制度2025」
【実施報告書】海外医療制度勉強会(オランダ編)
2025年7月17日、海外医療制度に関する勉強会を実施し、今回は「オランダ王国」の医療制度をテーマに取り上げました。
講師は弊社代表の溝口博重が務めました。
参加者は医療従事者、行政関係者、医療関連ビジネスに関心を持つ方々など計32名でした。
第1章:国家構造と制度文化の背景
オランダは立憲君主制と議会制民主主義を両立させた国家体制を採り、医療政策は議会および保健・福祉・スポーツ省(VWS)主導で立案・実行されています。
本章では国家の基本構造に加え、制度に対する国民の参加意識の高さ(保険選択・評価への積極関与)や、国民皆保険と市場原理を接続する制度文化を紹介しました。
第2章:2006年医療制度改革の構造転換
2006年に実施された医療制度改革(Zorgstelsel‐hervorming)では、公的保険と民間保険を融合した「競争的保険市場モデル」が導入されました。
全ての国民が民間保険会社と契約することを義務付けられた一方、国は制度設計と価格規制の役割を担い、「自由選択」と「制度平等」の両立が図られました。
市場原理を採り入れつつも、強力な公的規制のもとで医療の公平性と質の確保が追求されています。
第3章:義務化された自由選択モデルと制度的中立性
本章では、すべての国民が基本健康保険(Zorgverzekeringswet:Zvw)に加入義務を負う構造と、その保険会社を自由に選べる制度的特徴について解説しました。
保険者間にはリスク調整制度(Risk Equalization System)が導入され、慢性疾患や高齢者などハイリスク群を多く抱える保険者に対して、国が補助を行うことで保険設計の公正性を維持しています。
ただし、選別的プラン設計による「事実上のリスク回避行動」が一部で見られる点も課題として紹介しました。
第4章:医療提供体制とデジタル戦略
医療提供体制は以下の4つの小章に分けて解説しました。
α:Huisarts(家庭医)制度と紹介制
一次医療の基盤として、すべての住民に家庭医(Huisarts)が割り当てられます。
専門医にアクセスするには原則として家庭医の紹介が必要となる「ゲートキーパー制度」が採用されており、医療費の効率的抑制と適正化に寄与しています。
β:非営利病院とZBC(Zelfstandige Behandelcentra)
急性期や高度医療を担う公的病院のほか、日帰り手術や専門外来を担う独立型診療センター(ZBC)が増加しており、地域医療における機能分化と選択肢の拡大が進んでいます。
γ:薬局制度と薬剤費の統制
調剤薬局(Apotheek)は医師と独立しており、OTC(市販薬)販売との分離原則が維持されています。薬剤価格は政府と製薬業界による集団価格交渉制度により統制され、過剰支出の抑制が図られています。
δ:医療ITと患者参加ツール
全国規模の医療情報ネットワークであるLSP(Landelijk Schakelpunt)により、電子健康記録(EHR)が共有され、患者が自ら健康情報を管理するpHealth(personalized eHealth)との連携も推進されています。
第5章:QAC評価と国際比較の視点
オランダの医療制度をQuality(質)/Accessibility(アクセス)/Cost(費用)の観点から評価しました。
Quality:診療ガイドラインの普及、予防重視政策、専門医教育水準の高さにより、OECD諸国中でも高い医療の質を維持。
Accessibility:家庭医の存在による適切なアクセス制御が機能している一方、専門医紹介までの初期アクセスの遅延が課題として報告されました。
Cost:保険料と自己負担の適正配分がされており、GDP比医療支出はOECD平均水準(約10〜11%)。競争的設計により支出効率は高い水準を維持。
第6章:医師教育・診療報酬・長期ケアとの接続
医師養成制度はボローニャ・プロセスに準拠し、「学士(Bachelor)→修士(Master)」を経て、職能実習(AIOS)を含む段階的訓練を重視しています。
診療報酬は、DBC(Diagnosis Treatment Combination)制度により包括的に評価され、費用対効果に応じた資源配分が実現されています。
高齢化への対応として、介護保険制度(Wlz:Wet langdurige zorg)との制度的接続が重視され、医療・介護・福祉の統合的アプローチが政策的に推進されています。
第7章:質疑応答・参加者の声
勉強会の終盤には質疑応答とまとめの時間が設けられ、参加者同士による制度比較や実務への応用可能性に関する議論が活発に行われました。
参加者からは以下のような声が寄せられました。
「制度の持続可能性に対する設計思想が明確で、理論と現場の接続が見事だった」
「患者の役割が“受け手”から“選び手”へと転換されている点が印象的」
「日本の地域包括ケアシステムとも対照しやすく、学びが多かった」
次回予告
次回は東欧諸国で一番の医療制度と評価される「チェコ」の医療制度を取り上げます。
私もまったく知らんので、楽しみです。