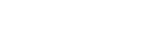新着情報
 Information
Information
【海外医療制度勉強会】「アイルランドの医療制度2025」
【実施報告書】海外医療制度勉強会(アイルランド編)
2025年9月18日、海外医療制度に関する勉強会を実施し、今回は「アイルランド共和国」の医療制度をテーマに取り上げました。
講師は弊社代表の溝口博重が務めました。
参加者は医療従事者、行政関係者、学生、医療関連ビジネスに関心を持つ方々など計48名でした。
第1章:国家構造と制度文化の背景
アイルランドは英国と同様に議会制民主主義・コモンロー(英米法系)を基盤としつつ、「国民は国家に依存しすぎない/自己責任と共助のバランスを重視する文化」が特徴です。
医療制度は英国NHSの影響を強く受けていますが、完全無料型ではなく、「所得に応じた二層構造(公的+民間)」を採用しています。
制度文化としては以下の三点が根付いています。
公平性(Equity)よりも「必要に応じた優先順位付け(Priority)」
国家運営の透明性・審議制(Public Accountability)
コミュニティ主導の地域医療(Community-based Care)
第2章:制度変遷と構造転換
アイルランド医療制度の歴史は以下の3フェーズに整理されます。
1)1947年「Health Act」~ 貧困層向け医療無料化(医療扶助型)
2)1970年代~ NHS型の公的医療+民間保険の併存体制へ
3)2000年代以降~ 「Sláintecare(スロンチャケア)」による医療費無料化の段階的拡大
現在は “完全無料NHSに向かう過渡期” にあり、特に GP初診料の無料化拡大 が進んでいます。
第3章:国民皆保険とリスク共有の仕組み
アイルランドには日本のような形式的な「皆保険制度」は存在しません。
代わりに、国民の約40%が「医療カード(Medical Card)」を保有し、公的医療を無料で受けられます。
その他の国民は自己負担(一部補助)か、民間医療保険(約45%加入)を利用します。
第4章:医療提供体制と地域ケア
α:プライマリ・ケア(GP制度)
GP(General Practitioner)がゲートキーパーとして機能し、登録制・紹介制により二次医療へアクセス調整します。
診療所はほぼ民間開業形態であり、国家との契約により公費診療を提供。
β:病院と公私混合体制
急性期病院の約80%は公立(HSE傘下)ですが、病院内に「公費ベッド」「民間ベッド」が混在しています。
民間保険加入者には優先的に病床が割り当てられるケースもあり、これが課題に。
γ:薬局制度と薬剤費補助
薬局は民営中心。所得に応じた上限負担制度(Drugs Payment Scheme)により、一定額以上は公費補助。
δ:長期ケアと在宅政策
高齢化に伴い、在宅ケア(Home Support Services)へのシフトが国家戦略。
Nursing Home(介護施設)は民間中心で、公費補助(Fair Deal Scheme)により入所費用をカバー。
第5章:QAC評価と国際比較
Quality(質):GP教育・専門医制度の質は高く、欧州でも上位水準。
ただし病院待機時間の長期化が恒常的な課題。
Accessibility(アクセス):プライマリケアは良好だが、専門医・手術待機が数ヶ月〜1年に及ぶ場合も。
Cost(費用):医療費GDP比は約7%で、日本より低水準。
一方、民間保険依存による影の医療費が大きい。
第6章:医師教育・診療報酬・長期ケア制度
医師教育:University College Dublin 等が中心。EU共通基準に基づき国際移動が容易。
診療報酬:GPは人口当たり定額(Capitation)+出来高(FFS)のハイブリッド。
病院はグローバルバジェット型(包括予算)。
長期ケア:介護保険制度はなく、医療保険と社会福祉の交錯領域として運用。
第7章:質疑応答・参加者の声
「公費+民間の二層構造が制度不信ではな選択肢として成立している点が興味深い」
「Sláintecareの無料化ロードマップは、日本の少子高齢化対応のヒントになる」
「地域包括ケアとは文化が違うが、コミュニティ主導型の支え合いが根強いと感じた」
次回予告
来月から第9期を開催します。
初回は「ニュージーランド」の医療制度を取り上げます。
世界初のユニバーサルヘルスを達成した事例として、その歴史と財源構造を深掘りします。