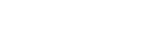新着情報
 Information
Information
【教養としての戦争と医療と法】ビスマルク外交とベルリン会議(1860年~1890年)
「教養としての戦争と医療と法」と題しまして、無料のオンライン勉強会を毎月最終週の火曜19時より企画開催しています。
https://geopolitics-war.peatix.com/
ご興味頂けるようであれば、是非ご参加ください。
昨今の世界情勢などもありますが、何事も歴史があります。
近代以降の国際情勢を学びながら、発見やら学びをしていければと思っております。
【講師】
緒方 健氏(鹿児島出身) 研究員
溝口博重氏(青森県出身) AMI&I代表取締役
【過去開催の動画視聴もできます】
#1ウェストファリア条約~国家主権~
#2絶対王政への反抗~フランス革命~
#3ナポレオン戦争~欧州近代史の始まり~
#4イタリア統一戦争
#5クリミア戦争
#6アメリカ独立戦争
#7アメリカ南北戦争
#8アヘン戦争
#9普仏戦争
#10ビスマルク外交とベルリン会議
第10回「教養としての戦争と法と医療」勉強会を開催しました
弊社主催の勉強会「教養としての戦争と法と医療」の第10回が開催されました。今回のテーマは「ビスマルク外交とベルリン会議」。
講師を務めたのは、弊社代表であり歴史と医療法の専門家である溝口博重です。
本講義では、19世紀後半のヨーロッパ外交において極めて重要な役割を果たしたビスマルク外交と、その集大成とも言えるベルリン会議(1878年、1884年)の意義について多角的な視点から解説が行われました。主な内容は以下の通りです。
1. ビスマルク外交の基本方針と背景
オットー・フォン・ビスマルクは、ドイツ統一を成功させた後、ヨーロッパの安定を維持するために巧妙な外交政策を展開しました。本講義では、ビスマルクが「均衡外交」によってフランスを孤立させながらも、ロシアやオーストリア=ハンガリーとの関係を調整し、戦争を防ぐためにどのような戦略を取ったのかを詳しく解説しました。
2. ベルリン会議(1878年)と東方問題
1877年から始まった露土戦争の結果、ロシアがオスマン帝国から大幅な領土を獲得し、ヨーロッパの勢力均衡が崩れる恐れがありました。この危機に対処するため、1878年にベルリン会議が開催され、ビスマルクが「誠実な仲裁者」として主導しました。本会議では、サン・ステファノ条約の修正が行われ、バルカン半島の国際秩序が再編されることとなりました。本講義では、ビスマルクの調停の巧みさと、その後のバルカン半島の不安定化への影響について分析しました。
3. ベルリン会議(1884年)とアフリカ分割
1884年から1885年にかけて開催されたベルリン会議は、アフリカ大陸の植民地分割に関する国際ルールを確立する場となりました。この会議では、ヨーロッパ列強がアフリカの植民地化を進めるにあたり、国際紛争を避けるための原則(「実効支配の原則」など)が制定されました。ビスマルクは当初ドイツの植民地獲得には消極的でしたが、最終的にはドイツ領南西アフリカ(現ナミビア)などを獲得し、帝国主義的政策への転換が見られました。
本講義では、この会議の決定が後のアフリカの政治・経済構造に与えた影響についても掘り下げました。
4. ビスマルク体制の崩壊とその影響
ビスマルク外交の成功にもかかわらず、彼が1890年に辞任した後、ドイツ帝国は積極的な対外進出を進め、ヨーロッパの緊張が高まりました。
本講義では、ビスマルクの外交戦略が後継者によってどのように変化し、第一次世界大戦へとつながる国際環境の変化を生み出したのかを分析しました。
5. 戦争・外交と医療の関連性
ビスマルク時代の戦争と外交が医療制度に及ぼした影響についても解説が行われました。特に、普仏戦争後のドイツにおける公衆衛生改革や、傷病兵のケアに関する国際的な動き、赤十字の役割についても取り上げられました。また、アフリカ分割後の植民地における医療体制の変遷についても議論されました。
今回の勉強会では、外交政策が戦争の抑止や国際秩序の形成にどのような役割を果たすのかについて、活発な意見交換が行われました。特に、「ビスマルクの外交手腕とその限界」についてのディスカッションが盛り上がり、参加者にとって非常に学びの多い時間となりました。
次回は、「清仏戦争と日清戦争」をテーマに開催予定です。詳細については追ってお知らせいたします。
今後も多くの方のご参加をお待ちしております。